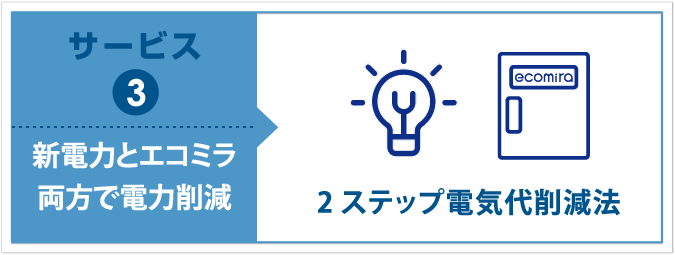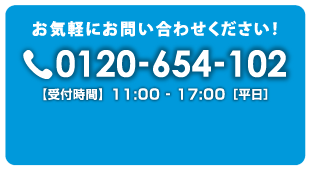快適性とドラフト感
空調機器は、居住空間をなるべく快適な状態にできるように設置されている。快適性を測る基準のひとつに、ドラフト感がある。ドラフト感とは、居住空間の平均温度と、人に当たった時の温度の差と、その風の速さを表す。冬の場合は、エアコンの風が天井から、吹いてきた温風が窓や壁に沿って冷やされて、人に当たると冷たく感じるのだ。これを、コールドドラフト(冷感ドラフト)という。
快適性の基準
ASHRAE(アメリカ暖房冷凍空調学会)では、室内の温度差とドラフトに対し、快適状態を表す指標として次の有効ドラフト温度θ[℃]を定義している。
θ=(tX-tC)-8(uX-0.15)
tX:室内の局所温度[℃]
tC:室内の平均温度[℃]
uX:室内の局所気流速度[m/s]
この有効ドラフト温度θが-1.7~+1.1℃で、かつ気流速度が0.35m/s以下の範囲内にあれば、座っている在室者の大多数が快適とされている。簡単に言えば、人の肌に当たった時の温度から、平均の部屋の温度を引いて、その時の風速から0.15引いた値を8倍して、さらに引いた値だ。
例えば…
部屋の平均温度が25度で、肌に当たった時の風速が、0.15m/sで、温度が24度であれば、θ=(24-25)-8(0.15-0.15)=-1℃となるので、快適の範囲内に収まっている。
環境による快適性の違い
しかし、これがどんな場所でも快適かというとそうでもない。極端な例だが電車の場合は、(JIS E 6603)日本工業規格として基準を定めている。

しかし、特急車両のように客室に長時間同じ姿勢で動きが少ない状態では、ドラフトを感じない静かな空調環境が望ましく、逆に通勤近郊車両では、たとえば猛暑のラッシュ時に車内に入ったときなど清涼感がありドラフトを感じる方が喜ばれる。このように、ドラフトの有無で快適空間かどうかを判断できないことがわかる。
快適空間とは
人にとっての快適空間とは、その人の体調や、状況により様々なパターンがあり、一概に温度と湿度、風速だけでは、判断できない。ただ言えることは、長く滞在する居住空間において、温湿度の変化が少ない空間が人にとって快適な空間と言える一つの条件ではないだろうか。