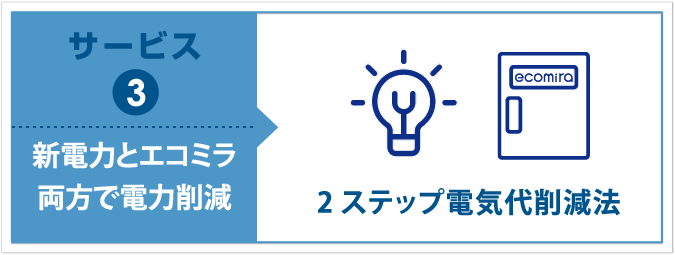理想の話が終わり、省エネが「インフラ」になった瞬間
COP30で何が決まったのか、と聞かれても、
正直に言えば「これだ」と一言で言える派手な答えはない。
世界を驚かせる新しい目標が掲げられたわけでもなく、
すべてを一気に変える決断がなされたわけでもなかった。
ただ、COP30全体を通して感じた空気は、
これまでの会議とは明らかに違っていた。
各国が語っていたのは、
「より高い理想」よりも、
今ある目標をどう実行するか、
そして
猛暑や電力不足の中で、社会をどう止めないか
という現実的な問いだった。
COP30は、世界を一気に変える場ではなく、
うまくいかない前提で、それでも壊れずに続ける道を探す場
になっていた。
この空気を見て、私はある確信に至った。
理想は、役目を終えたのだと思う
2015年のパリ協定のころ、
世界にはまだ
「理想を共有すれば前に進める」
という期待があった。
1.5℃、2℃。
数字は明快で、方向性もはっきりしていた。
あの時代は、
正しいことを言うこと自体に意味があった
のだと思う。
けれど10年が経ち、
私たちはもう知ってしまった。
正しいだけでは、現実は動かない。
技術は時間がかかり、お金は十分に回らず、
政治はいつも揺れる。
COP30の会場にあったのは失望ではない。
幻想が剥がれたあとの静けさだった。
いま問われているのは、「止まらないかどうか」
最近、議論の中であまり聞かれなくなった問いがある。
「何%削減できるのか」
「CO₂を何トン減らせるのか」
代わりに増えてきたのは、こんな問いだ。
猛暑の夏でも、病院は動くのか。
電力が足りないとき、工場は止まらないのか。
都市は、ちゃんと機能し続けられるのか。
評価軸が、
削減量から“継続できるか”へ
静かに移っている。
この問いに答えられない技術や政策は、
どれだけ立派でも、主役にはなれない。
そのとき、省エネの意味が変わった
この流れの中で、
省エネの見え方は大きく変わった。
かつての省エネは、
どこか地味で、少し我慢を伴うものだった。
しかし今、省エネは
最後に残る選択肢になりつつある。
新しい発電所がすぐには作れなくても、
送電網を簡単に強くできなくても、
国際合意が揺れても、
それでも社会を止めないために、
まず頼られるのが省エネだ。
特に、人の努力や意識に頼らず、
自動で、静かに、負荷を下げる省エネは、
もはや「対策」ではなく
社会を支える前提条件になっている。
気づけば、省エネはインフラになっていた
インフラとは、
普段は意識されないものだ。
止まらなければ話題にならず、
止まったときに初めて、
その価値に気づく。
電力が足りなくなった瞬間、
社会を守るのは
スローガンや理想ではない。
使い方を制御する力だ。
この意味で、省エネはもう
環境対策の枠を超えている。
道路や上下水道、堤防と同じように、
「止まったら困るから備えるもの」
になっている。
理想は終わった。しかし、前に進んでいる
COP30を見て感じたのは、
希望が消えたということではない。
むしろ、
現実に耐える形へと進化し始めた
という感覚だった。
脱炭素は、
信じる人だけの取り組みでは続かない。
信じていなくても、
損をしたくない人が自然に動く。
そんな仕組みでなければならない。
そして、現場から見えていること
COP30を見て、
私は静かに、しかしはっきりと確信した。
これまで「省エネ」と呼ばれてきたものの中には、
時代とともに役割を終えていくものもあるだろう。
我慢を前提にしたもの、
人の善意に頼るものは、長くは続かない。
一方で、
止めずに、無理をさせず、
気づかれないまま社会を支える省エネは、
これからも残り続ける。
現場を見ていると、本当に困ったときに求められるのは、
立派な理想ではなく、「今日をどう乗り切るか」という現実的な答えだ。
COP30は、そのことを
世界が共有し始めた場だった。
そして私は、
日々の現場で積み重ねてきた
“止めない省エネ”こそが、
これからの社会を静かに下支えする
インフラの一部になっていく、
そう感じている。
省エネは、
理想のための手段ではなく、
現実の社会を守るための基盤になったのだ。