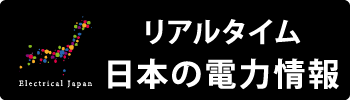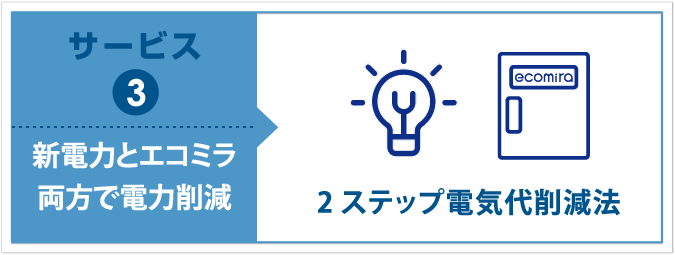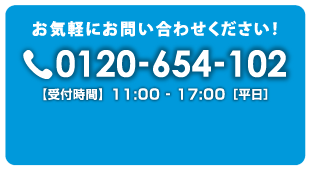デススパイラル Death Spiral(負の連鎖)
欧米諸国を中心に、太陽光発電などの大量導入によって送配電事業の費用回収漏れが構造的に連鎖していくことが指摘されています。 太陽光や蓄電池による自家消費により設備計画策定時や電気料金設定時よりも系統電力の伸びが鈍化 減少すると、電力会社にとって自家消費などによる直接的な収益悪化に加えて下記のような①~⑤を繰り返してしまう負の連鎖が起こってしまいます。
① 系統電力需要の減少
② 系統利用率の悪化
③ 託送料金の引き上げ
④ 電気料金の上昇
⑤ さらなる自家消費の拡大

特に米国などではネットメータリング制度のもとで太陽光発電などの導入が進んだのですが、近年では顧客負担の不公平性(太陽光所有者は相殺分の託送費用は払わないため、結果的に太陽光発電所有者以外に託送コストがしわ寄せされる)の問題もあり、太陽光発電所有者への新しい負担などネットメータリングの見直しの動きも始まっています。
ネットメータリング制度 Net Metering
自家消費を目的とする小型分散型電源の導入促進のために海外の一部の国·地域で導入されています。電気の売買を差し引き、 繰り越しなども行って、小売料金を計算する制度のことを指します。アメリカなどではこの制度の導入が家庭用太陽光発電など小型分散型電源の普及に大きな役割を果たしました。
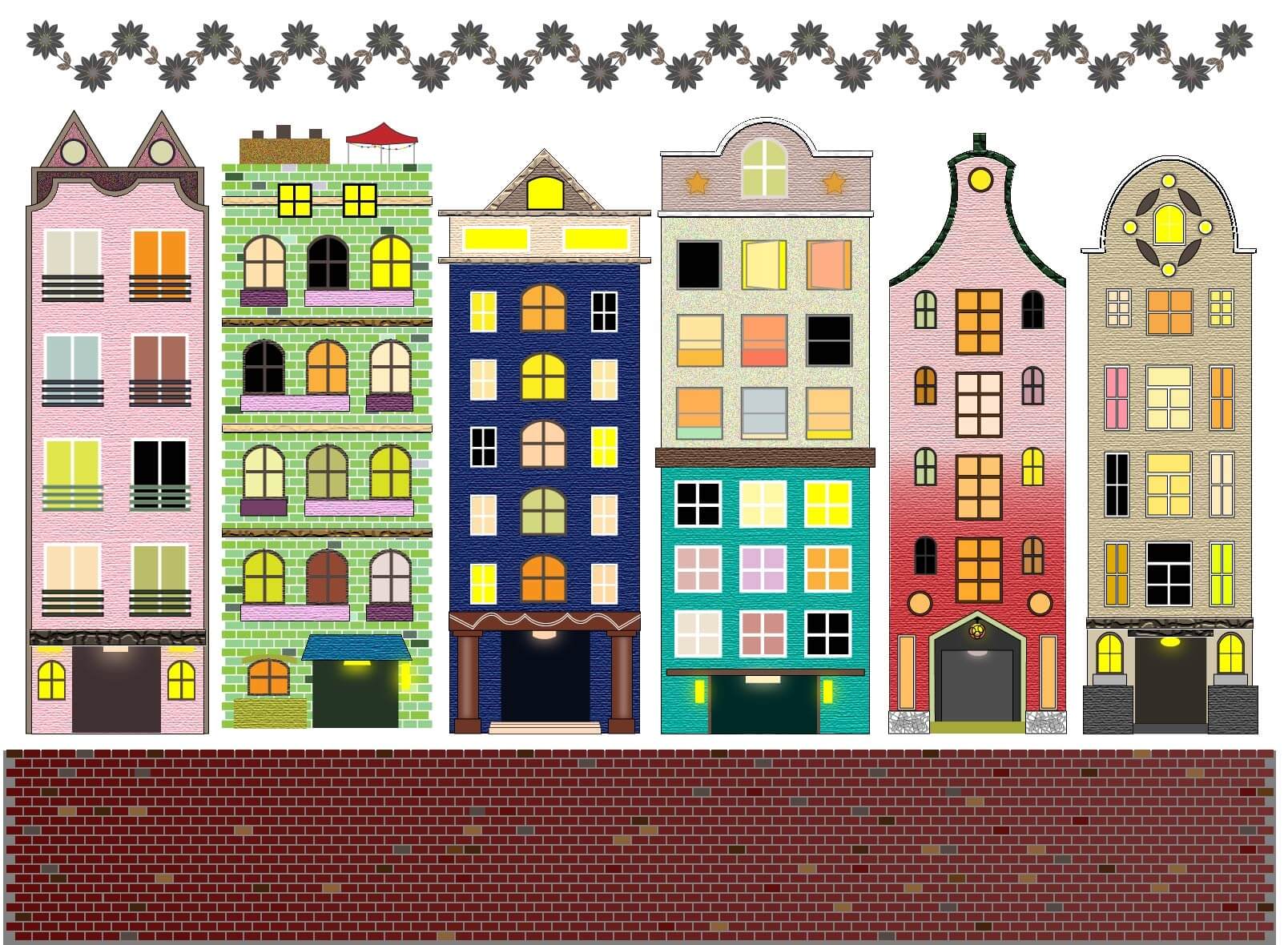
この制度では、自宅の屋根に設置した太陽光発電などからの余剰分を系統側に供給(逆潮流) する場合、供給した分だけ電力メーターを戻すことができ、事実上、電力会社の売電価格と買電価格(余剰電力を購入する価格)が同じとなり、売りが多ければ翌月に繰り越して小売料金を削減することもできます。

この結果、ネットメータリングは、電気料金に上乗せされている送配電網の維持費やバックアップ費用(託送料金)などの固定費負担を逃れていることになります。さらに、電力会社は販売電力量の減少で回収できなくなった固定費を、託送料金などの値上げで回収することになり、その負担がまた太陽光発電を設置していない需要家の電気料金へ転嫁されるといった問題点があります。
発電逼迫時のみ節電できることが大事
様々な設備をコストをかけて設置し、電気を生み、蓄電し、自家消費することも一つの手段ですが、今あるインフラを利用しながら、託送料金をみんなで少しずつ負担しながら、最大需要電力を減少させることが、まず最初に取り組むべきことだと思います。なぜなら設備投資できない人たちの負担が益々重くなるからです。他国の失敗に日本は学ぶべきだと思います。